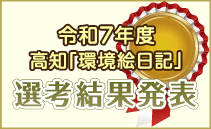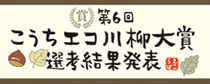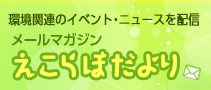- 管理運営団体:特定非営利活動法人 環境の杜こうち
- 〒780-0935 高知県高知市旭町三丁目115番地 こうち男女共同参画センター3F
- TEL:088-802-7765 FAX:088-802-2205
学習プログラム 詳細情報
| 所属:氏名 | 石川妙子 |
|---|---|
| プログラム名 | 川の生きもの調べ |
| 学習のねらい | 川に入り、生きものを採取し名前を知ることにより、河川水質を判定します。 また、川を五感で感じ取り、川と川の周りの環境を考えます。 |
| おすすめポイント | 川で遊ぶ子どもがめっきり少なくなってしまい、川への関心が 薄れています。 思い切り川に浸かって、自分たちの生活と川が繋がっていることを 実感できます。 |
| 活動の分野 | |
| 学習の方法 |
|
| プログラムの内容 | 1.水生昆虫を中心とした河川底生生物の解説、採取方法の解説(10分) 水生昆虫の定義、底生生物と生息環境、生物学的水質判定と化学的な水質検査の違いを解説します。 網、ピンセット、バケツを使い、生物を採取する方法を話します。 また、川の中での安全確保について注意を促します。 2.実際に川に入り、生きものを採取。(30〜45分) 川に入り、石を持ち上げたり川底をかき混ぜたりして、石の表面や網に入った生きものをピンセットでつまみ、バケツの中に入れます。瀬を中心に採取しますが、流れの緩いところや、草の生え際なども探します。高学年で時間の余裕があるときは、パックテストや流速の測定もしてもらいます。  3.水温・川の様子、川の周りの様子などを調査票に記入する。採取した生きものを観察し、生きものの名前を調査票に記入する。(30〜45分) 河原や教室等で、採取した生きものをテキストを参考に調べます。調査票にその日の川の様子や、パックテスト等の水質、調べた生きものを記入します。屋内でテレビモニター等を使用できる場合は、マイクロスコープで生物を拡大して解説します。 4.指標生物を用いて水質判定をする。(5分) 調査票に記入した指標生物により、水質を4段階で判定します。 5.川の周りの様子との関係を考える。 時間があれば、護岸、ダム、森林と川の生きもの・水質の関係を話します。 |
| 対象者 |
|
| 参加人数 | 30名以下が望ましいです。 |
| 実施場所 | 河川(瀬のあるところが望ましい)・まとめをする場所(河原・学校・公民館等) |
| 実施時期 | 1年中。日時は相談の上。 |
| 所要時間 | 2時間前後が望ましいですが、相談の上プログラムを調整できます。 |
| 使用する機材等 | |
| 必要経費 | |
| 注意すること | |
| 参加者の感想など | |
| 講師から一言 |